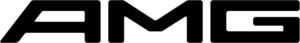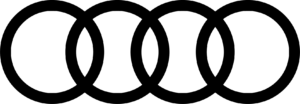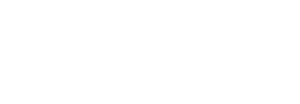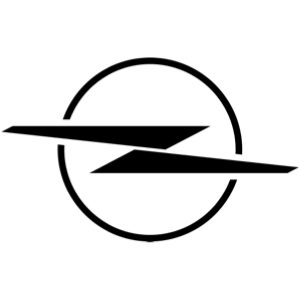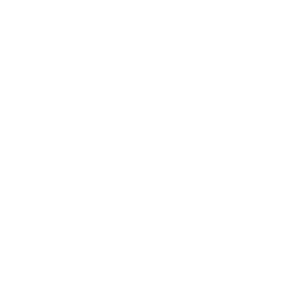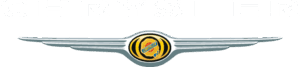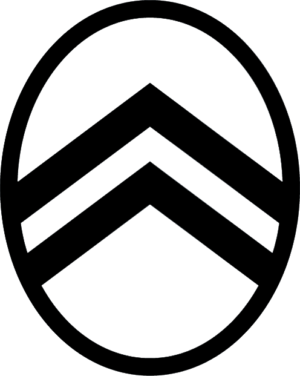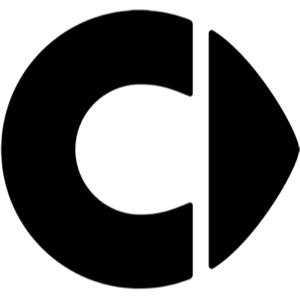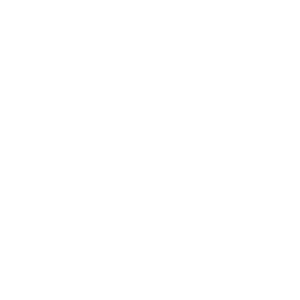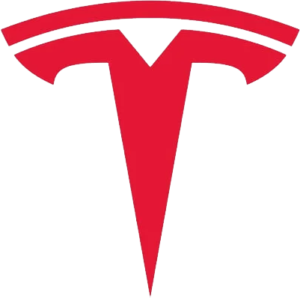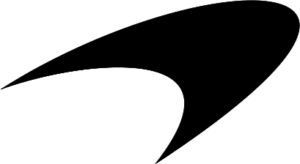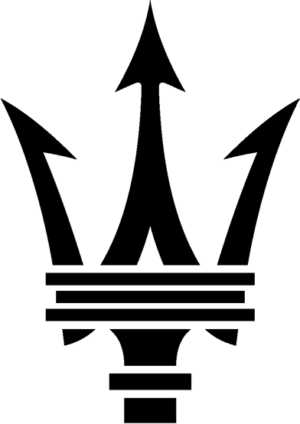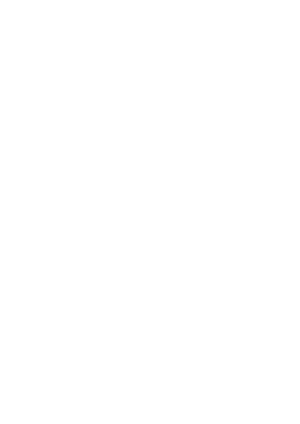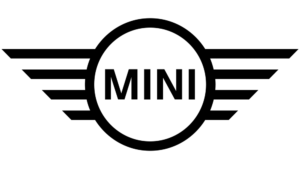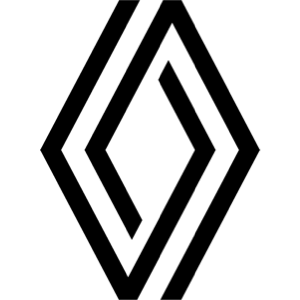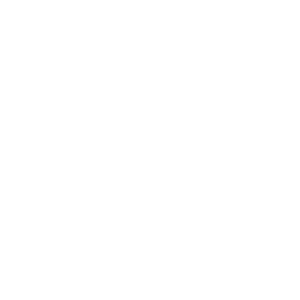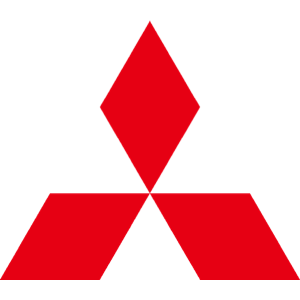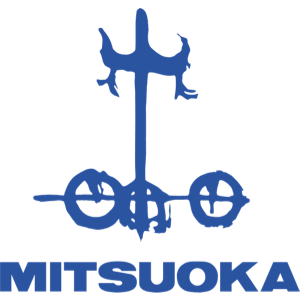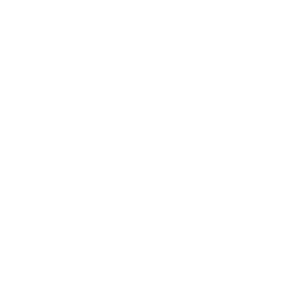スクエアな造形と5.0リッターV8スーパーチャージャー。自社設計エンジンを積む初代レンジローバー・スポーツは、現代の洗練とは異なる力強さを持つ。時代を超えて残る“英国の粋”を味わう一台。
純英国設計エンジン
角張ったボディラインを眺めていると、速度という概念が遠くに思える。ゆったりと走る姿が似合うクルマだ。
だが、アクセルを踏み込んだ瞬間、その印象はあっけなく覆される。
5.0リッターV8スーパーチャージャー──当時のレンジローバー史上、最も強力なエンジン。カタログスペックでは510ps、625Nm。スーパーチャージャーの過給が立ち上がるタイミングは驚くほど自然で、加速の波が途切れることはない。
レンジローバースポーツがデビューした当初、その心臓部にはBMWやフォードの設計が流用されていた。しかし2009年のマイナーチェンジを境に、状況は大きく変わる。
新たに搭載された5.0リッターV8は、ジャガー・ランドローバーが完全自社設計した初のエンジンだった。
フォード傘下でジャガーとランドローバーが統合され、その共同開発体制の中から生まれた“純英国設計”のユニットである。
前期型のBMW系V8は性能こそ申し分なかったが、どこか無機質だった。そこにジャガーという名門スポーツカーメーカーの感性が加わったことで、エンジンに“味”が生まれた。音の立ち上がりや回転の伸びに、機械ではなく人の意図を感じる。
この5.0リッター・スーパーチャージドは、まさにその象徴だ。当時のレンジローバー史上、最強のスペックを誇りながらも、数字以上に熱を感じる。自社開発第一世代のエンジンにかける気迫が、踏み込むたびに伝わってくる。
現在、レンジローバーのエンジンは自社製Ingeniumシリーズと、再び提携したBMW製ユニットが主流になった。
そう考えると、この世代の“自分たちの手で作った最強のV8”を積む一台は、時代の節目に立つ特別な存在として、いっそう味わい深く思えてくる。
薄れない存在感
角ばったボディラインには、どこか懐かしさがある。
直線と面で構成されたスクエアなフォルムは、セカンドレンジローバーほどの無骨さはないが、現行モデルのような滑らかさもない。
現代のレンジローバーが“面の美しさ”で魅せる存在なら、この世代は“線の力”で個性を放つ。造形の違いが、そのまま時代の空気を映しているようだ。
セカンドレンジほどクラシックではなく、現代の快適さを備えながら、どこかネオクラシック的な香りをまとっている。
ボディカラーは「バリ・ブルーメタリック」。一見すると明るいネイビーだが、光の角度によって紫が差すように色が揺らぐ。鮮やかさと深みが同居する、不思議な魅力を持ったカラーだ。
日陰では落ち着いた青に、陽が当たると鮮烈なブルーに。さらに夕暮れ時には、ほんのり紫を帯びた艶を見せる。レンジローバーらしい品格を保ちながらも、どこか遊び心を感じさせる珍しい色味で、人と違う一台を求める人にはちょうどいい“さりげない個性”になっている。
そして、ドアを開けると、淡いベージュのレザーが柔らかく光を返す。
ちょうど現代のレンジローバーへと通じる、ラグジュアリーSUVの礎を築いた時代。英国らしい美学とクラフトマンシップが、細部にまで息づいている。
その誠実な作り込みが、スクエアな外観と響き合っている。
まだまだ楽しめる
近年のレンジローバーは、ラインの多くを削ぎ落とし、曲面と光の移ろいで存在感を示すようになった。それはラグジュアリーSUVの未来を示す、完成された美しさだ。
そんな時代の潮流の中で、あえてこのスクエアなレンジローバーに乗る。ネオクラほど古くなく、日常での快適さを保ちながら、“少し前の時代の空気”をまとっている。
ボディサイズは全長4.8メートル未満。現行のヴェラールよりも短く、数字で見れば意外なほどコンパクトだ。それでもスクエアなデザインのおかげで実際より大きく見え、レンジローバーらしい重厚な佇まいを失わない。
街中でも取り回しやすく、インフォテイメントや装備も現代の基準で十分に実用的。日常の足としても、遠出の相棒としても成立するバランスがある。
バリ・ブルーメタリックという珍しい色に、最上位グレードならではの上質な内装、そして純英国設計の5.0リッターV8エンジン。
ボディの艶も内装の張りも失われておらず、年式を感じさせない。さらに2013年から2025年まで、2年おきの整備記録簿が残っており、整備履歴も明確だ。
これからも安心して、その走りと質感を存分に味わえる。
歴史に思いを馳せながら、もう二度と作られることのない大排気量エンジの鼓動を味わう。そんな時間そのものが贅沢な体験だ。
SPEC
レンジローバースポーツ 5.0 V8 スーパーチャージド
- 年式
- 2010年
- 全長
- 4,795mm
- 全幅
- 1,935mm
- 全高
- 1,785mm
- ホイールベース
- 2,740mm
- 車重
- 約2,600kg
- パワートレイン
- 5.0リッター V型8気筒 スーパーチャージャー
- トランスミッション
- 6速AT
- エンジン最高出力
- 510ps/6,000rpm
- エンジン最大トルク
- 625Nm/2,500〜5,500rpm

河野浩之 Hiroyuki Kono
18歳で免許を取ったその日から、好奇心と探究心のおもむくままに車を次々と乗り継いできた。あらゆる立場の車に乗ってきたからこそわかる、その奥深さ。どんな車にも、それを選んだ理由があり、「この1台のために頑張れる」と思える瞬間が確かにあった。車を心のサプリメントに──そんな思いを掲げ、RESENSEを創業。性能だけでは語り尽くせない、車という文化や歴史を紐解き、物語として未来へつなげていきたい。