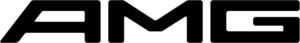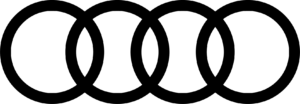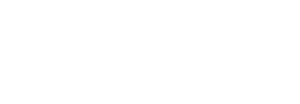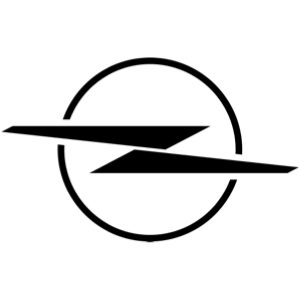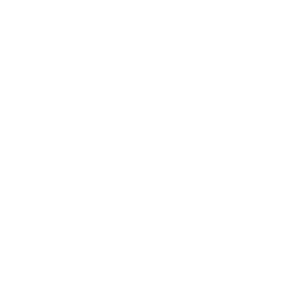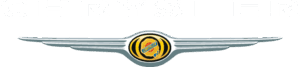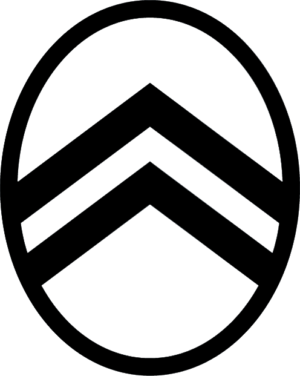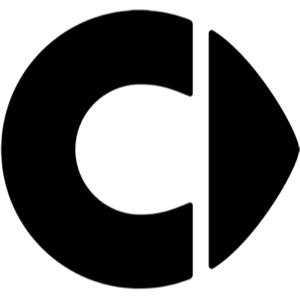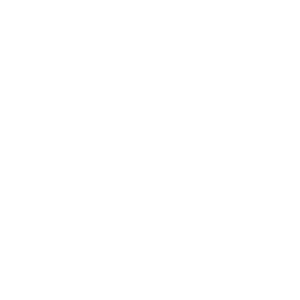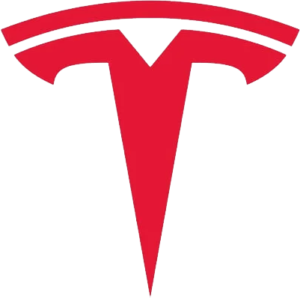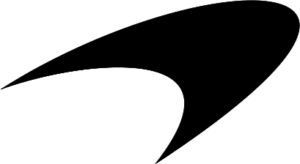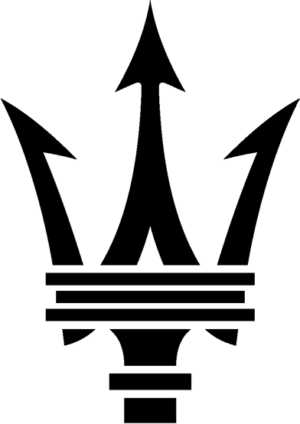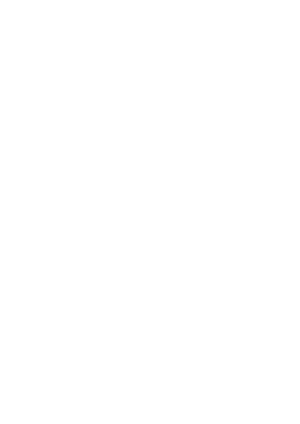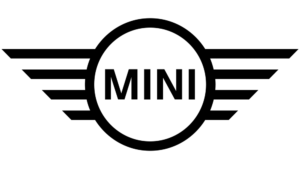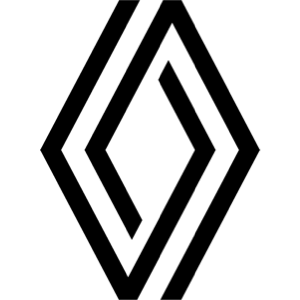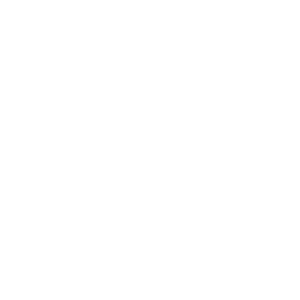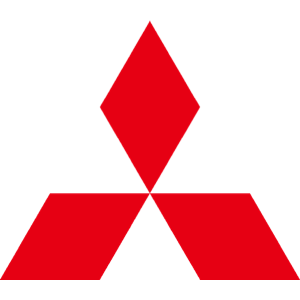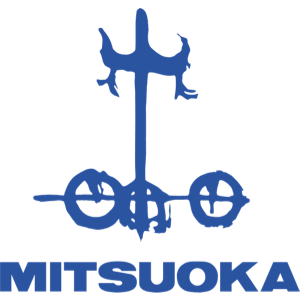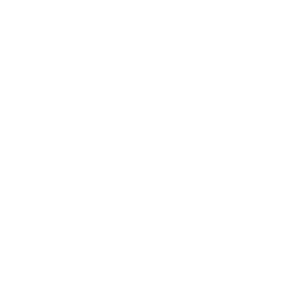三菱GTOは、速さを競うためのスポーツカーではない。オートマと4WD、そして90年代のハイテクが生んだのは、腕を誇らせない走りの余裕。いま乗ることで、その贅沢さが立ち上がる。
オートマであること
この三菱 GTO 3.0 SRに乗って、最初に意識させられるのは、オートマであるという事実だ。
だがそれは、スポーツカーとしての妥協ではない。むしろ、このクルマがどこを目指していたのかを、もっとも端的に示している。
GTOは、ドライバーに技量を要求しない。
変速操作に集中する必要も、常に緊張感を保つ必要もない。その代わりに、クルマそのものが状況を読み取り、淡々と最適な状態を保ち続ける。
アクセルを踏み込めば、3.0リッター自然吸気V6が無理のない力で車体を前に押し出す。4WDは路面状況を過度に意識させることなく、姿勢を安定させる。すべてが過不足なく、主張しすぎずに機能する。
この感覚は、いわゆるスポーツカー的な高揚とは少し違う。
GTOはドライバーを試さない。腕を誇示する場面を用意しない。その代わりに、クルマとしての完成度で、こちらを納得させてくる。
オートマであることは、GTOを「戦うスポーツカー」から「任せられるラグジュアリー・スポーツ」へと押し上げている。その余裕こそが、90年代にこのクルマが目指していた場所なのだと思う。
アメリカンGT的な立ち位置
GTOをどう捉えるか。その答えとして「和製アメリカンスポーツ」という表現がしっくりくる。ただし、コルベットではない。カマロだ。
一点突破の性能でヒーローになる存在ではなく、大きく、重く、力があり、それを日常の延長線で使えるクルマ。その距離感が、GTOにはよく似ている。
ボディは大柄で、車重もある。軽快に振り回すタイプではない。だが、直線や緩やかなカーブで感じる安定感は、まさにアメリカンGT的だ。
そこに、日本車らしい精密さが重なる。操作系は雑ではなく、挙動も理屈に忠実だ。荒々しさ一辺倒ではなく、技術で整えられたマッチョさがある。
その混ざり方が、純粋なアメ車とも、従来の国産スポーツとも違う独特の立ち位置を生んでいる。
心地よい“ズレ”
GTOは、90年代のハイテクスポーツカーだ。それも、実験的な存在ではなく、本気で未来を見据えて作られたタイプのハイテクである。
目指していた方向性は、ドライバーの腕を磨くものでも、ましてやクルマがドライバーを育てることでもない。
道具の側を最適化することで、誰でも性能を引き出せるようにする。その発想も、どこかアメリカ的な合理性に近い。
フルタイム4WDと電子制御サスペンションを中心に、走りの質そのものをクルマ側で整えていく。
当時の三菱は、ドライバーの腕に委ねるより、道具の完成度で性能を引き出すという選択をしていた。その結果として、GTOは重く、複雑で、やりすぎだと評されることもあった。
だが、電子制御が当たり前になったいま、その評価は反転する。
現代のクルマは、誰もが無意識のうちに制御の恩恵を受けている。GTOが目指していた世界は、時間をかけて標準になった。
ただし、GTOのハイテクは、まだ完全に不可視化されていない。制御が介入している気配が残り、クルマが何をしようとしているのかが、感覚として伝わってくる。
それが、いま乗ると「味」になる。
速さを競うための道具ではない。ドライバーを育てるための教材のような存在でもない。余裕という贅沢を楽しむために用意されたクルマ。
その思想は、効率と合理性が極まった現代だからこそ、逆に新鮮に映る。
90年代のハイテク思想を、成熟したいまの感覚で受け取る。
その“ズレ”が、驚くほど心地よい。

中園昌志 Masashi Nakazono
スペックや値段で優劣を決めるのではなく、ただ自分が面白いと思える車が好きで、日産エスカルゴから始まり、自分なりの愛車遍歴を重ねてきた。振り返ると、それぞれの車が、そのときの出来事や気持ちと結びついて記憶に残っている。新聞記者として文章と格闘し、ウェブ制作の現場でブランディングやマーケティングに向き合ってきた日々。そうした視点を活かしながら、ステータスや肩書きにとらわれず車を楽しむ仲間が増えていくきっかけを作りたい。そして、個性的な車たちとの出会いを、自分自身も楽しんでいきたい。