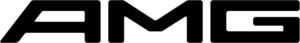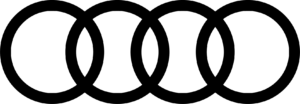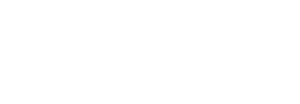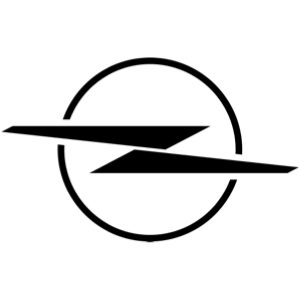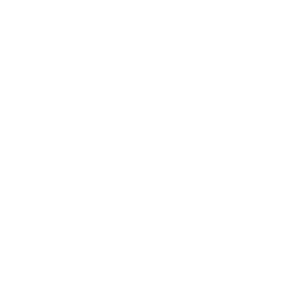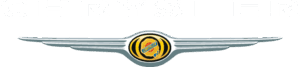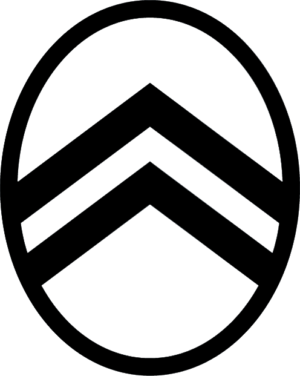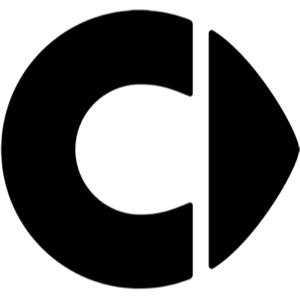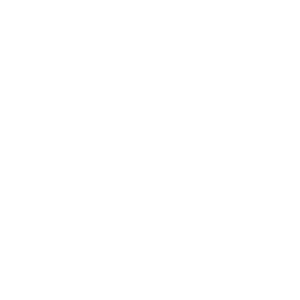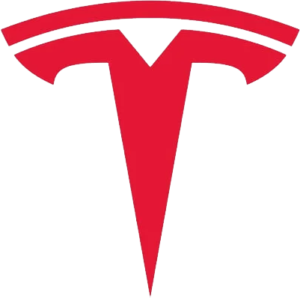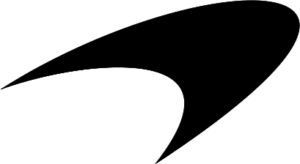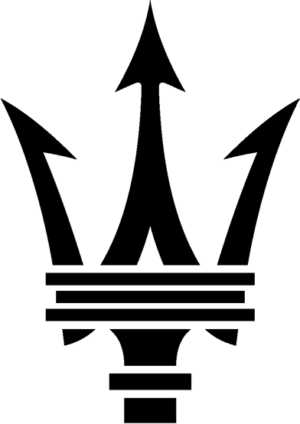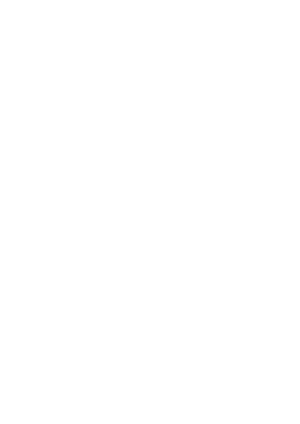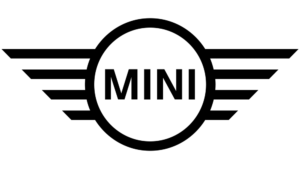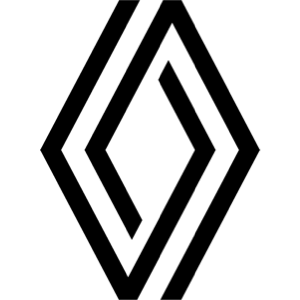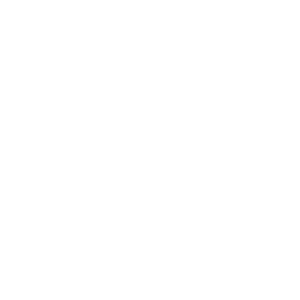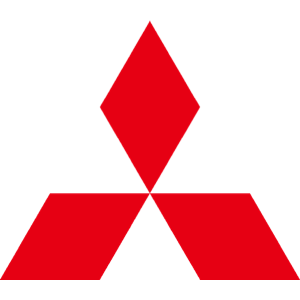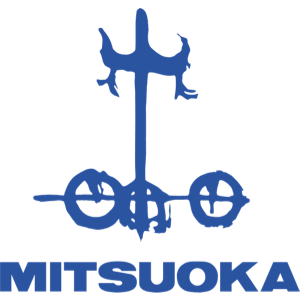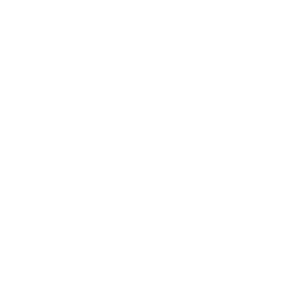前回のテスラ・モデル3に続く、2度目の長距離EV試乗。今回はポルシェ・タイカン、その中でも実用性を大きく押し広げた「クロスツーリスモ」だ。
クロスツーリスモとは
高められた地上高、ルーフレール、フェンダーの樹脂パーツ。
ひと目では「ポルシェらしい」よりも、「ポルシェとしては珍しい」要素が先に目に入る。
だが数秒眺めていると、筋肉質なフェンダーラインや張り詰めた面構成が、やはりポルシェそのものだと気づく。
タイカンは2019年に登場したポルシェ初のBEVグランドツアラー。その実用性とロングツーリング性能を押し広げる形で、クロスツーリスモは2021年に追加された。
言うなれば、ポルシェ流の電動5ドアCUVだ。
今回の個体はドロマイトシルバーメタリック。光のあたり方で穏やかにも鋭くも見える独特の色で、タイカンの有機的な曲線を自然に浮かび上がらせる。クロスオーバーらしい力強さを与えるオフロードデザイン20インチホイールとも相性がいい。
そして何より、2025年1月登録のほぼ新車。構えるなという方が無理だ。乗る前から高揚感がじわじわと上がってくる。
スポーティなのに開放的
ドアを開けて座った瞬間、この車が正真正銘ポルシェであることが伝わってくる。
ブラックよりわずかに明るいグレーのレザーは、硬派さよりも上質さが前に出る仕立て。ダッシュボードは水平基調で、視界がひらけている。前席の開放感は想像以上だ。
センターコンソールの高い位置づけやメーターのレイアウトは、明らかにスポーツドライビングを意識した作りだが、窮屈さはまったくない。
そしてスポーツクロノパッケージのアナログ時計がダッシュトップにあるだけで、気分が一段変わるのも必然だ。
後席に移ると、さらに驚く。
タイカンはクーペライクなラインの印象が強いが、クロスツーリスモは頭上空間に余裕がある。そこに巨大なパノラマルーフが組み合わさり、実寸以上の広さを感じる。
全体の質感は、どちらかといえばパナメーラ寄り。
“電動スポーツカーの内装”ではなく、“ポルシェのラグジュアリーサルーンの文脈を持つEV”という方が近い。
スタートボタンを押すと音もなくシステムが立ち上がる。はやる気持ちを抑え、アクセルペダルにそっと力をかけた。
違和感のない操作感
最初に感じたのは“音”だ。
ペダルを踏み込むと、背後からわずかなモーターのうなりが聞こえてくる。
この“後ろから聞こえる感覚”が妙にポルシェらしくて、思わず頬が緩む。
前回乗ったモデル3(RWD)は、ほとんどモーター音がなかった。
あれはあれで気持ちよかったが、タイカンはあえて音の存在を調律しているように思える。
スポーツモードを選ぶとその傾向はさらに強まり、加飾されたEVサウンドが加速と一体になる。
そして圧倒されたのは、加速と減速の自然さ。
エンジン車とEV車の違いから来る違和感がほとんどない。回生ブレーキも滑らかで、加速もリニア。
電動らしい瞬発力はあるが、唐突さはまったくない。
これまで乗ってきた“エンジン車の延長線上にある運転感覚”のまま扱える。
テスラが“新しい乗り物”なら、タイカンは“これまでの自動車を電気で進化させた存在”。
そしてこのタイカンは、電動化してなおポルシェの文脈をしっかり保っている。
あくまでポルシェ
ほぼ5mの全長、ほぼ2mの全幅。
数字だけ見れば巨大な車だが、前方視界の良さとリアアクスルステアのおかげで取り回しは驚くほど良い。
「本当に必要か?」と思っていたソフトクローズドアも、一度半ドアを救ってもらうと考えが変わる。静粛なEVだからこそ、こうした細部の上質さが効いてくる。
スポーツクロノ、リアアクスルステア、BOSE、パノラマルーフ、マトリクスLED、ソフトクローズ。
実用性と快適装備がバランス良く揃い、クロスツーリスモ本来のオールラウンダー性を強調する内容だ。
SUVの実用性、ワゴンの積載性、スポーツカーの走り、EVの静けさ。
そのすべてを1台で完結させてしまう、“オールインワン”という表現がまさにしっくりくる。
これは“EVのポルシェ”ではなく、“ポルシェが作ったEV”。
そう感じさせる完成度だった。
SPEC
ポルシェ・タイカン クロスツーリスモ4
- 年式
- 2025年
- 全長
- 4,974mm
- 全幅
- 1,967mm
- 全高
- 1,409mm
- ホイールベース
- 2,907mm
- 車重
- 約2,220kg
- パワートレイン
- 前後2基の交流同期モーター
- トランスミッション
- 前:シングルスピード
後:2速ギアボックス - システム最高出力
- 476ps/650Nm

中園昌志 Masashi Nakazono
スペックや値段で優劣を決めるのではなく、ただ自分が面白いと思える車が好きで、日産エスカルゴから始まり、自分なりの愛車遍歴を重ねてきた。振り返ると、それぞれの車が、そのときの出来事や気持ちと結びついて記憶に残っている。新聞記者として文章と格闘し、ウェブ制作の現場でブランディングやマーケティングに向き合ってきた日々。そうした視点を活かしながら、ステータスや肩書きにとらわれず車を楽しむ仲間が増えていくきっかけを作りたい。そして、個性的な車たちとの出会いを、自分自身も楽しんでいきたい。