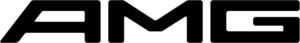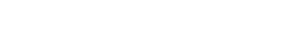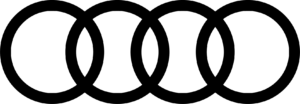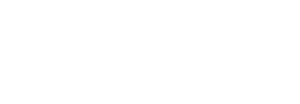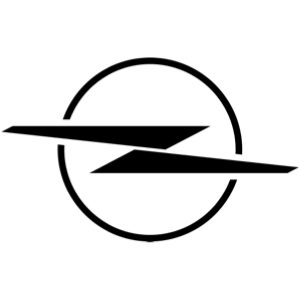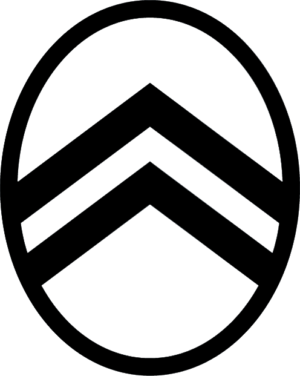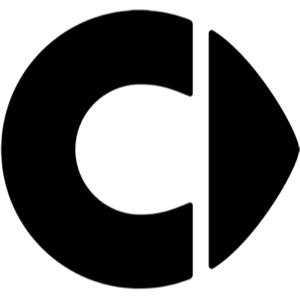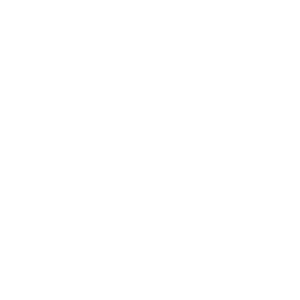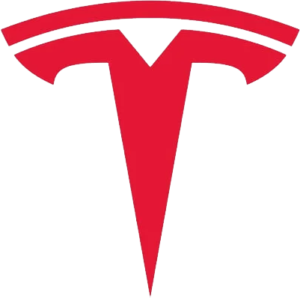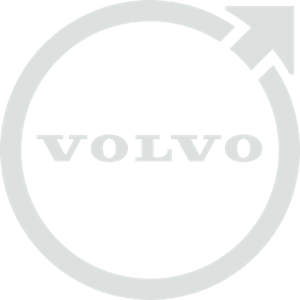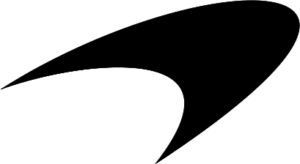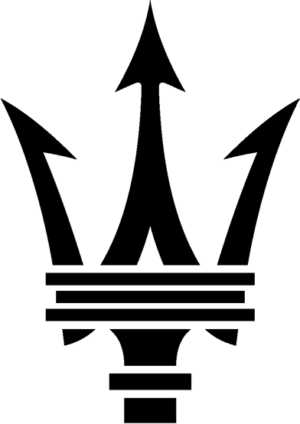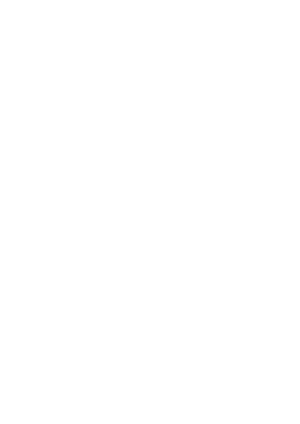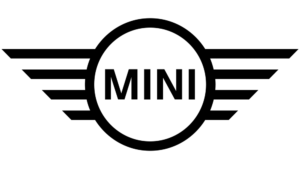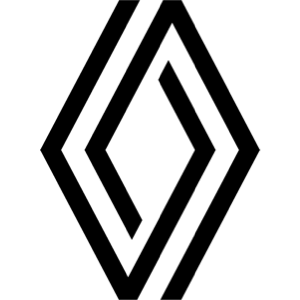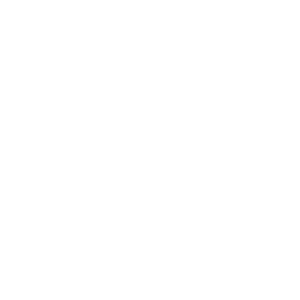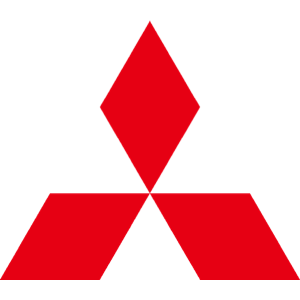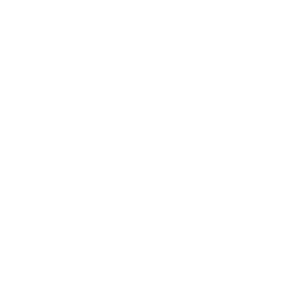デフォルメの効いたデザインと、正直すぎる足まわり。そしてターボ。40年前のホットハッチに詰まっていたのは、速さではなく、“ちいさな冒険”の楽しさだった。
INDEX
窓を全開にして
なんだろう、無性に窓を全開にして走りたくなる。
どこかの街で41度を記録したというニュースが流れていた、記録的猛暑日だというのに、なぜか「エアコンを使ったら負けだ」と思ってしまう。
だから乗り込んで最初にやることは、手動でクルクルと窓を開けること。電動じゃないから、1〜2秒で一気に全開にできる。せっかちな人にはとてもありがたい。
当然ながら、熱気は容赦なく吹き込んでくる。けれど、汗ばんだ体に風が当たるあの一瞬の清涼感を求めて、ついアクセルを踏みこんでしまう。
風の音と、小さなエンジンが懸命に回る音。それを身体で浴びながら走る感覚が、なんとも心地いい。このクルマには、そんな“遊び方”がよく似合う。
ちなみにこの個体の名誉のために言っておくと、エアコンはちゃんと効く。エアコン装備がまだ一般的ではなかった時代のクルマにもかかわらず、しっかりと冷たい風が出る。
それでも窓を開けて走りたくなるのは、きっとこのクルマに宿る冒険心のせいだろう。
ちょうど40年前のクルマ
現代のクルマにはないデザイン。いや、過去にもこんな作り物めいた存在は、他にそうそうなかったはずだ。
まるでマンガのページから──それも、鳥山明の世界から飛び出してきたようなデフォルメ感。
短い全長に対して、背の高いキャビン。小さなタイヤ。どこか“寸詰まり”にも見える、そのユーモラスなプロポーションが、このクルマのキャラクターを決定づけている。
それに加えてこのターボIIは、オーバーフェンダーと大きなフロントスポイラー、ボンネット上のインタークーラー用スクープが戦闘力の高さを物語る。もうそれだけで早く走らせたくてウズウズしてくる。
リアハッチには、当時のディーラーや、年季の入ったJAFのステッカーが無造作に貼られている。貼り方も含めて、当時は決して“おしゃれ”とは言えなかったかもしれない。けれど、こうして数十年の時間が経った今見ると、それらはまるでアンティークサインのように味わい深い。
バンパーの塗装には、目を凝らさないとわからない程度の細かなヒビ割れが浮かんでいた。けれどそれも、ヴィンテージギターのウェザーチェックのようで、むしろかっこいい。「これが自分の車だったらここは直さないな・・・」などと妄想がはかどる。
そんなふうに外観だけで夢中になっていたら、ふと気づく。このクルマ、ちょうど40年前に生まれたんだということに。
それなのに、驚くほど状態がいい。外装には目立つ傷もなく、中を見てもスイッチ類やメーターまわりの文字が掠れていない。シートもしっかりと弾力を保っており、シートベルトのたるみもない。
もちろん、経年劣化は隠せない。だが、それは単なる古びではなく、時間が生んだ質感として、このクルマの魅力に溶け込んでいる。
40年という歳月を経てもなお、歴代のオーナーたちがこの一台を丁寧に乗り継ぎ、大切にしてきたことが実感として伝わってくる。
ターボが“効いている”
短いボンネットの奥に搭載されるのは、1.2リッター直列4気筒ターボ。最高出力は110ps。数字だけを見れば控えめにも思えるが、現代の軽自動車より軽い、わずか700kg台のこの小さなボディには十分なパワーで、アクセルを踏めば軽やかに加速する。
ターボが効いているという実感は、残念ながら私にはわからなかった。それでも、ステアリングの奥、メータークラスターの中央にある「TURBO」と書かれたブーストインジケーターが上がり下がりする様にワクワクする。
よくあるアナログ式のプレッシャーゲージではなく、デジタル表示なのも男心、いや、“男の子心”をくすぐる。ターボが効いている気分になれるこの表示だけで、どこまでも行けそうな気がしてくる。
計器としての役割はもちろん、気分を盛り上げる演出装置としても、文句なしの120点満点だ。
こうしたギミックひとつにも、ホンダらしい本気と遊び心が感じられる。
もっと運転していたい
シフトの節度や、クラッチのミートポイントは、現代のスポーツカーのように「カチッ」と決まるものではない。
クラッチをつないでも、どこか緩く、ふわりと走り出す。けれど、その曖昧さが走りの自由度を高めてくれる。
無理に速く走らなくても楽しい。でも気づけば、「次はもっと上手く走れるかも」と、つい試行錯誤している。
それはまるで修行のようでもあり、自分との戦いに近いような感覚でもある。そうした小さな挑戦と手応えが、このクルマとの時間をいっそう楽しくしてくれる。
足回りは、路面の凹凸を遠慮なく伝えてくる。少し舗装が荒れているだけで、車体全体が跳ね、きしみ、そして揺れる。
それでもアクセルは緩めない。パワステなしの、細くて重たいステアリングを握りしめ、全身で車体をコントロールする。
厚手のセミバケットシートが、その正直すぎる足まわりの突き上げを、やわらかく受け止めてくれる。
舗装路なのに、感覚はほとんどオフロード。街中でさえ、ちょっとした冒険になる。
汗をかきながらの試乗を終え、エンジンを切った。それでもまだ頭の中では試行錯誤が続いている。もっと運転していたくなるクルマだった。
このクルマだからこそ
このクルマに乗って感じた楽しさは、もしかしたらマニュアル車すべてに言えることかもしれない。もっと純粋なスポーツカーのほうが、速くて、正確で、走りの質も高いだろう。
けれど、そういう話じゃない。
このシティには、デザインも、サウンドも、排気ガスの匂いも、そしてこれまで積み重ねてきたストーリーも含めて、このクルマだけの空気感がある。
だからこそ、つい「エアコンは使わない」なんて、どうでもいいルールを自分に課したくなる。そして、そんな行動のひとつひとつが、ちいさな冒険になる。
それは、子どもの頃に初めて自転車を手に入れたときのような、自由と期待に満ちた体験だ。
そんな、原始的な楽しさが詰まったクルマだった。
SPEC
ホンダ・シティ ターボII
- 年式
- 1985年式
- 全長
- 3380mm
- 全幅
- 1570mm
- 全高
- 1470mm
- ホイールベース
- 2220mm
- 車重
- 約735kg
- パワートレイン
- 1.2リッター 直列4気筒ターボ
- トランスミッション
- 5速MT
- エンジン最高出力
- 110ps/5500rpm
- エンジン最大トルク
- 160Nm/3000rpm

中園昌志 Masashi Nakazono
スペックや値段で優劣を決めるのではなく、ただ自分が面白いと思える車が好きで、日産エスカルゴから始まり、自分なりの愛車遍歴を重ねてきた。振り返ると、それぞれの車が、そのときの出来事や気持ちと結びついて記憶に残っている。新聞記者として文章と格闘し、ウェブ制作の現場でブランディングやマーケティングに向き合ってきた日々。そうした視点を活かしながら、ステータスや肩書きにとらわれず車を楽しむ仲間が増えていくきっかけを作りたい。そして、個性的な車たちとの出会いを、自分自身も楽しんでいきたい。