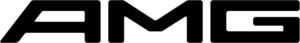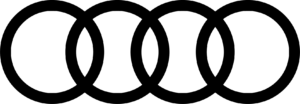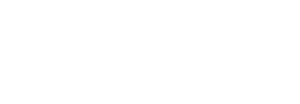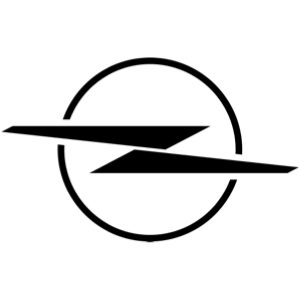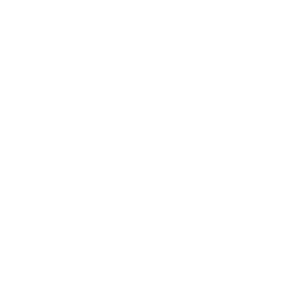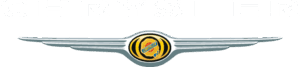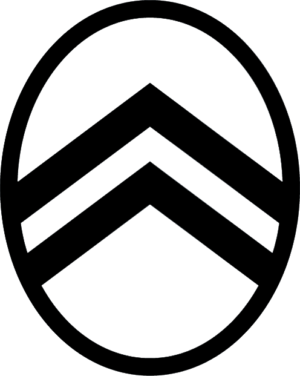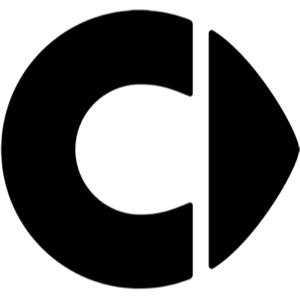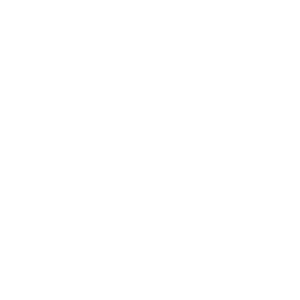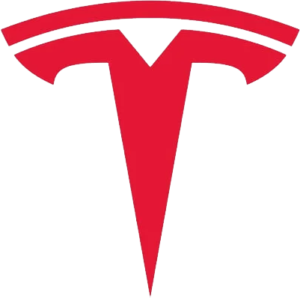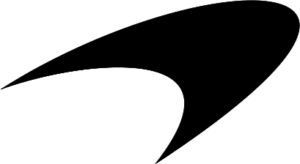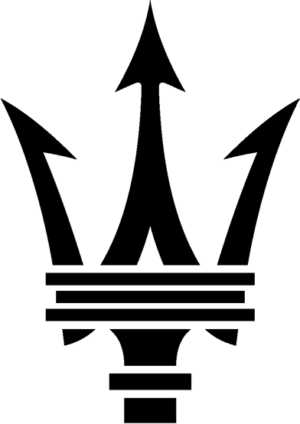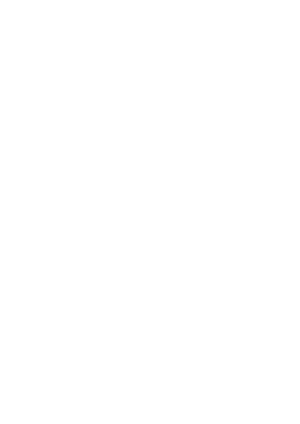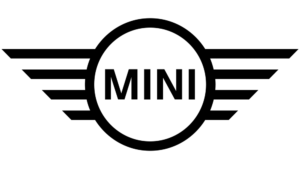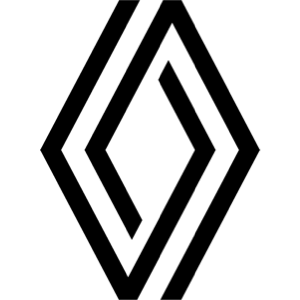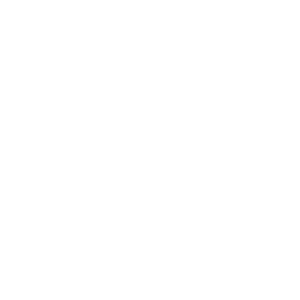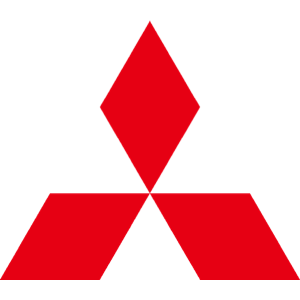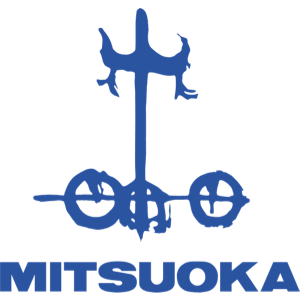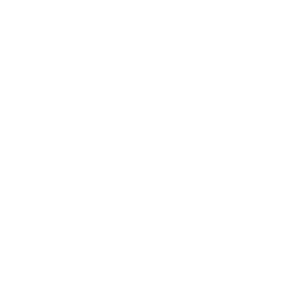GT Rはサーキットを目指さなくても、日常のストリートで十分すぎる刺激を放つ。操作の余地と緊張感を抱えたまま走る、その危うさこそがこの一台の本質だ。
レースカーを公道で
メルセデスAMG GT Rを前にすると、どうしても比較対象としてポルシェ・911GT3の存在が頭をよぎる。
どちらもサーキット走行を強く意識して生まれたマシンであり、レースカーに近い思想を市販車へと落とし込み、公道を走れる形に仕立てている点では立ち位置は近い。
仕上がりの精度や操作の正確さにおいて、GT3の完成度はきわめて高い。その挙動には、ポルシェが長年積み上げてきたノウハウが、そのまま反映されている。
だが、このGT Rに乗ると、その比較は次第に意味を失っていく。
アクセルを踏んだ瞬間、背中から伝わるV8の圧力と、車体全体が前に押し出される感覚が、理屈よりも先に感情を揺さぶる。
速さそのものではなく、昂ぶりの質が違う。どれだけ心拍数を上げてくるか。どれだけドライバーの神経に直接触れてくるか。その方向性が異なる。
サーキットに行かなくてもいい。限界を探らなくても、このクルマは十分すぎるほど刺激的だ。
レースカーを公道で操るという喜びを、日常のストリートで味わえる。
公道レーサーにこそ
GT Rは、行き先をサーキットに設定しなくても成立する。
走り出すのは、いつものストリート。信号があり、制限があり、流れに合わせて走る、ごく普通の道だ。
GT Rは、そこで意外なほど静かに振る舞う。暴れないし、急かさない。アクセルを深く踏み込まなければ、クルマも深く踏み込んでこない。
ただし、常に張りつめた空気だけは残っている。
足元には、まだ解放していない力が確実に眠っている。それを使うかどうかは、こちら次第だ。
幹線道路での合流や追い越し。ほんの一瞬、アクセルを踏み足しただけで、景色の密度が変わる。
重要なのは、そこから先だ。これ以上を求めなくても、すでに刺激は十分にある。
GT Rは、タイムを削るための装置ではない。日常のストリートで、レーシングカーの気配を抱えたまま走るための存在だ。
わざわざサーキットへ行く必要はない。行けば確かに使い切れるのだろうが、行かなくても、このクルマはすでに十分すぎるほど尖っている。
GT Rは、サーキットを目指さない“公道レーサー”にこそ似合う。
トラクションを“管理する”
センターコンソールの上、エアコン吹き出し口の下に、ひとつだけ異質な存在がある。
TCと書かれた黄色い小さなダイヤル。AMGの中でも、GT R系のみに与えられた装置「AMGトラクションコントロール」だ。
操作はいたって単純で、つまみを左右に回すだけの、直感的なアナログ操作だ。
だが、走り出せば違いはすぐに分かる。
少し緩めるだけで、アクセルを踏み足したときの反応が変わる。立ち上がりでリアがわずかに遅れ、タイヤが一瞬だけ滑る。
その先は、すべてアクセル次第だ。戻せば収まり、踏み続ければ滑りが続く。クルマが勝手に抑え込む感じはなく、操作がそのまま挙動に返ってくる。
一般的なトラクションコントロールは、滑り始めた瞬間に介入するための装置だ。
GT Rのそれは違う。どこまで滑らせるかを、あらかじめドライバーに委ねている。制御は残っているが、出しゃばらない。だからこのクルマは、刺激を均してしまわない。
このダイヤルは、GT Rというクルマの性格をそのまま表している。
完成度よりも、操作の余地。安心よりも、緊張感の濃度。
AMGが最も尖っていた時代の本気は、派手な演出ではなく、こうした静かな仕組みに残っている。
時代の断面としてのGT R
2017年という時代は、ひとつの境目だった。電動化が本格化する直前、V8がまだ主役でいられた最後の空気が残っていた頃だ。
このGT Rは、その空気をそのまま閉じ込めた存在だ。
過剰なまでのV8、サーキット直系の思想、刺激を均さない制御。
AMGグリーンヘルマグノというボディカラーも、この個体を象徴する要素のひとつだ。
マット塗装ならではの陰影が、GT Rの筋肉質なボディラインを強調し、面の起伏をはっきりと浮かび上がらせる。
この色はGT Rのカタログやプロモーションでも前面に使われた、いわば“顔”となるカラー。特別な演出ではなく、GT Rというモデルの性格を、そのまま視覚化したような色と言える。
走行距離は5,000km。コレクションとして成立する保存状態であることは間違いない。そのうえで、このGT Rという稀有な存在を、実際に走らせて楽しめる余白が残っている点は、なお魅力的だ。
GT Rは、単なるハイパフォーマンスカーではない。AMGというブランドが、最も過激だった時代の思想を、色濃く残す一台だ。
完成度ではなく、昂ぶりを。安心ではなく、緊張を。
GT Rは、そういう価値観を選んだ人間のためのクルマだ。

河野浩之 Hiroyuki Kono
18歳で免許を取ったその日から、好奇心と探究心のおもむくままに車を次々と乗り継いできた。あらゆる立場の車に乗ってきたからこそわかる、その奥深さ。どんな車にも、それを選んだ理由があり、「この1台のために頑張れる」と思える瞬間が確かにあった。車を心のサプリメントに──そんな思いを掲げ、RESENSEを創業。性能だけでは語り尽くせない、車という文化や歴史を紐解き、物語として未来へつなげていきたい。