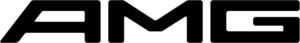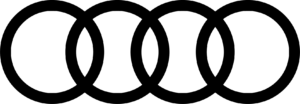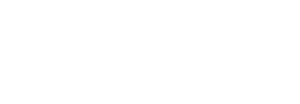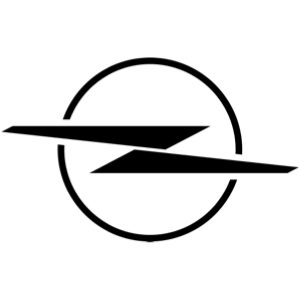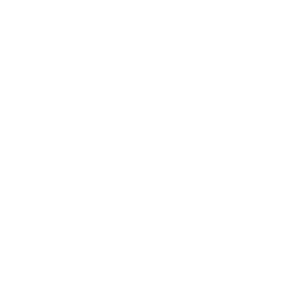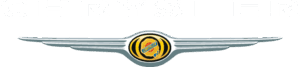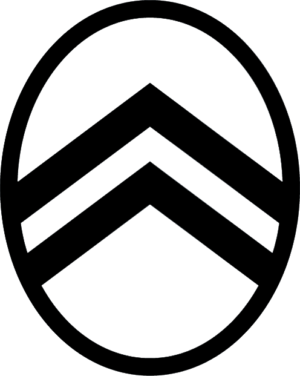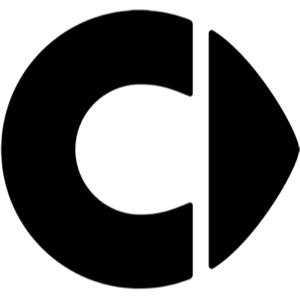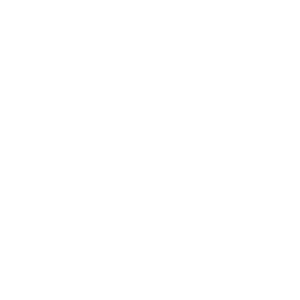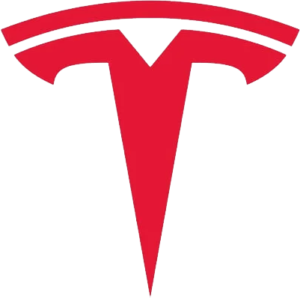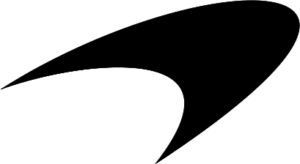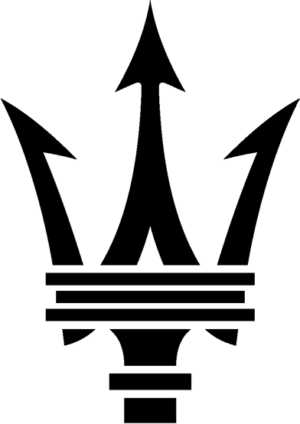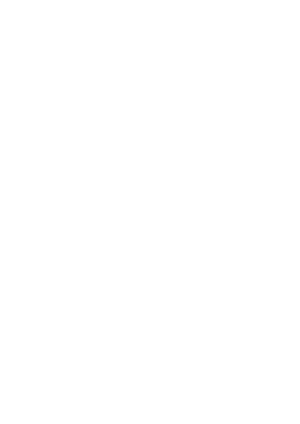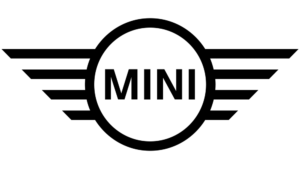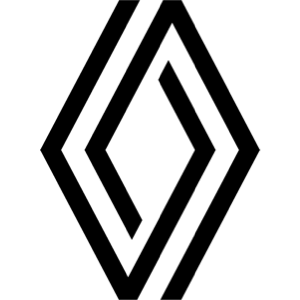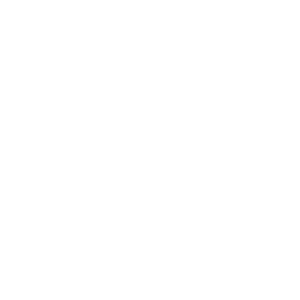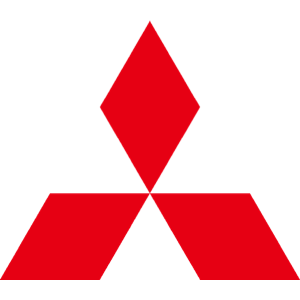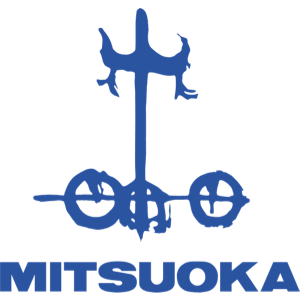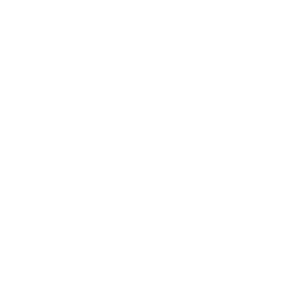流行でも、ノスタルジーでもない。ただ古いクルマに、どうしようもなく惹かれる瞬間がある。1988年式クラウンは、記憶にないからこそ新鮮で、想像以上に誠実だった。静かな完成度が、「今こそクラウン」と思わせる一台だ。
初めて触れるような
古いクルマが好きだ。
新しい車の最新技術に触れる喜びや快適性の高さも、もちろんクルマ選びの楽しみのひとつではある。だが、ときどき、どうしようもなく古い車に乗りたくなる瞬間がある。理由はない。もう不治の病のようなものだ。
このクラウンを一目見たときも、まさにそんな感覚だった。
いわゆるヤングタイマーと呼ばれる車たちより、ほんの少し古い佇まい。記憶に引っかかる既視感がなく、だからこそ新鮮に映る。そして、その年式からは想像できないほどの状態の良さ。
「この車に乗りたい」
そう素直に思えたのは、この昭和の車に、初めて触れるもののような新しさを感じたからだと思う。
ふと、旧車好きの自分が頭の中で囁いてくる。「今こそクラウンなんじゃないか」と。
ヤングタイマーの少し前
ヤングタイマー。90〜00年代にかけての独特なデザイン、当時ならではの空気感。それらが、若い世代を中心に新鮮さを伴って受け入れられ、ひとつの潮流になった。
新鮮ではあるが、どこかで見たことがある。リアルタイムを知っている、あるいは記憶の片隅に残っているからこそ、そのエモさが魅力として立ち上がってくる。
それに対して、この1988年式クラウンは、そこからさらに一世代前に位置する。
記憶と結びつく風景がない。だからこそ、懐かしさよりも先に「知らなかった」という感覚が立ち上がる。
角張ったボディラインに、さりげなく配されたメッキモール。昭和の空気をまといながらも、奇をてらうことはない。
室内も同様だ。
長方形のメーター、細身で大径のステアリング、整然と並ぶオーディオやエアコンのスイッチ類。現代の車ではあまり見かけなくなった構成だが、操作に戸惑うことはなく、自然に走り出せる。
クラシックカーと呼ぶにはまだ早い。しかし、昭和という時代を体験として知らない目には、十分に“クラシック”として映るだろう。
フラッグシップの走り
1989年にセルシオが登場する直前、このクラウンはトヨタのフラッグシップサルーンだった。
搭載されるのは、2.0リッターの直列6気筒エンジン。
2リッターであっても4気筒ではなく、あえて6気筒を与える。その選択自体が、このクルマの立ち位置を端的に物語っている。
効率よりも滑らかさ、合理性よりも品位。
バブル期に開発・販売されたモデルらしく、当時ならではの贅沢さが感じられる。高級車とはどうあるべきか。その思想から一切ブレることなく、設計されていたことが伝わってくる。
エンジンは前に出しゃばることなく、一定の回転域で淡々と仕事をする。アクセルを踏み込めば、必要な分だけ、過不足なく車体を前へと運ぶ。その振る舞いに、無理はない。
日本の社会の中で使われることを前提としたフラッグシップセダン。誰が乗っても違和感がなく、どこへ出ても恥ずかしくない。そのために求められたのが、この滑らかさと贅沢さだったのだろう。
状態の良さが後押しする
内装は、外装色に合わせてチョイスされたのか、ほぼネイビーで統一されている。パネルやシートはもちろん、フロアマット、シフトセレクター、ドアの内張に至るまで、紺色の世界が広がる。
シートのモケットは、クラシックホテルのソファを思わせる手触りだ。クラウンのマークが編み込まれた純正レースも残されている。それらが今なお瑞々しさを保っていることが驚きだ。
この個体の走行距離は12,000km。単に距離が少ないというだけでなく、大切に扱われてきた時間が、そのまま車に刻まれていることがはっきりと伝わってくる。
一目で“昔の車”だと分かるが、それでいて、都会の街並みにも、自然の風景にもよく馴染む。
毎日乗る車としての最適解ではないかもしれない。それでも、日常の足として使うことに不安はない。そこには、長年積み重ねられてきたトヨタ車ならではの安心感がある。
他の人と被らない選択として。
白や黒ではなく、ネイビーという色が持つ上品さ。
そして、それを静かに支える、トヨタならではの誠実なつくりと、この個体の状態の良さ。
流行でも、ノスタルジーでもない。「今こそクラウン」と言いたくなる理由は、案外シンプルだ。
このクルマが、「いいクルマ」だったからだ。

中園昌志 Masashi Nakazono
スペックや値段で優劣を決めるのではなく、ただ自分が面白いと思える車が好きで、日産エスカルゴから始まり、自分なりの愛車遍歴を重ねてきた。振り返ると、それぞれの車が、そのときの出来事や気持ちと結びついて記憶に残っている。新聞記者として文章と格闘し、ウェブ制作の現場でブランディングやマーケティングに向き合ってきた日々。そうした視点を活かしながら、ステータスや肩書きにとらわれず車を楽しむ仲間が増えていくきっかけを作りたい。そして、個性的な車たちとの出会いを、自分自身も楽しんでいきたい。