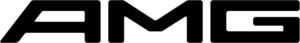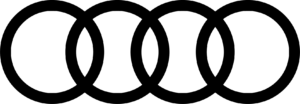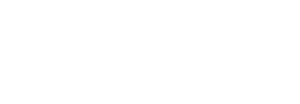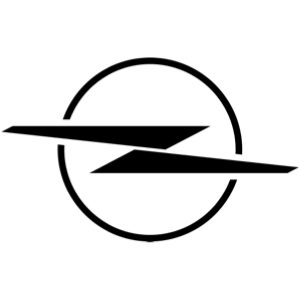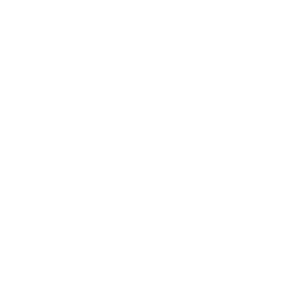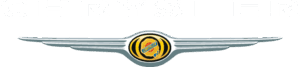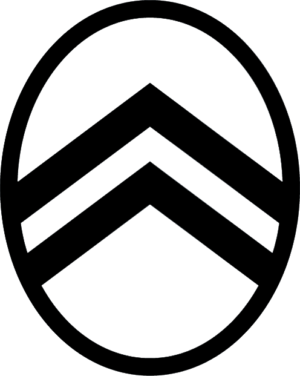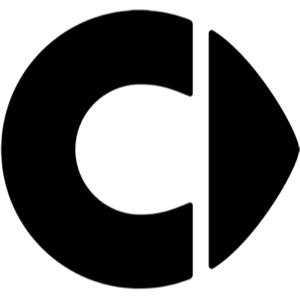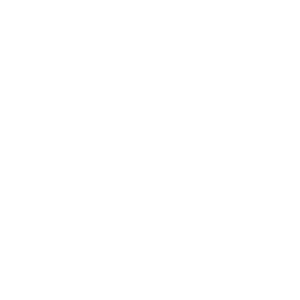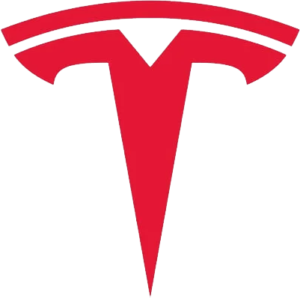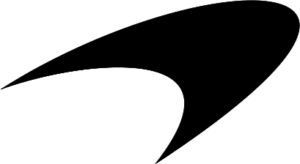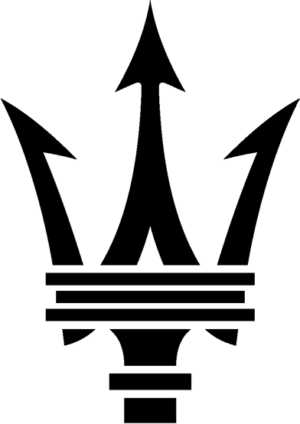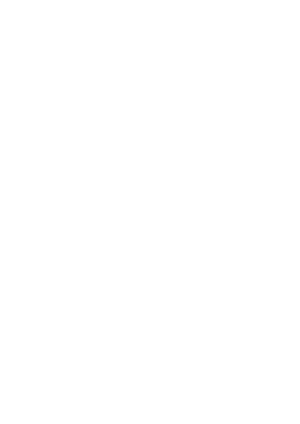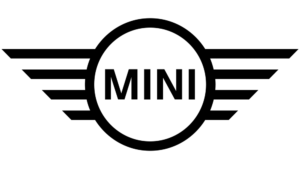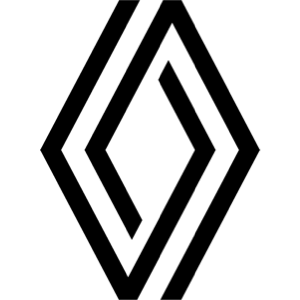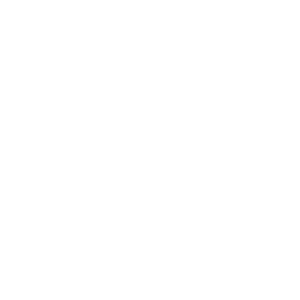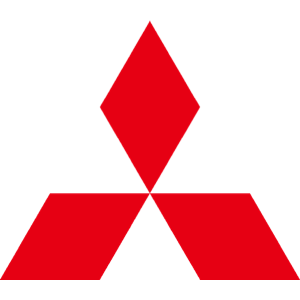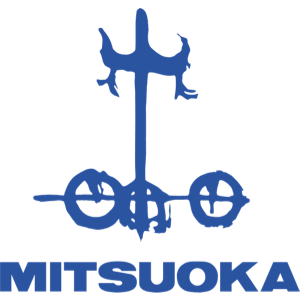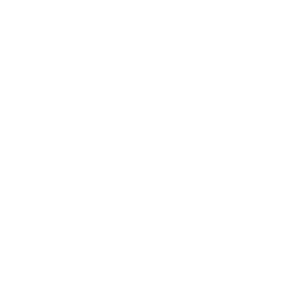終売から時間が経ち、見慣れた存在になったザ・ビートル。だが冬の冷たい空気の中でルーフを開けると、この小さなオープンカーが持つ高揚感が鮮やかに蘇る。忘れられつつある今こそ選びたくなる一台だ。
忘れかけていた存在
ザ・ビートルの販売が終了したのは2019年。あれから5年以上が過ぎ、街で見かけても特に気に留めることはなくなった。
むしろ、ニュービートルの丸みを帯びた姿のほうが「あっ」と目を引くし、今乗るならそっちのほうが趣がある──そんなふうに思っていた。
だが、改めてザ・ビートル、それもカブリオレに触れると考えが変わる。
タイプ1やニュービートルと比べればスタイリッシュの度合いが強く、「ビートルらしさが薄まった」という評価がつきまとう。しかしそれは、あくまで同じ血筋同士での比較でしかない。
一般的な車の中に置けば、このスタイルは今もなお異彩を放つ。そしてサターンイエローのボディカラーはその個性をいっそう引き立てる。
同色パネルの内装と、電動ソフトトップを備えたカブリオレ。日常を少し明るくしてくれる存在感がここにはある。
冬のオープンは“我慢”ではない
試乗したのは、季節が急に進んだ11月半ば。
冷え込んだ空気が窓を曇らせる朝、最初の信号待ちで迷わずルーフを開けた。
薄く刺すような冷気と、背中を包むレザーシートの温かさ。
オープンと同時にシートヒーターとエアコンが自動で起動し、思いもしなかった“おもてなし”がじんわり身体に広がる。
冬のオープンは、決して我慢大会ではない。
上空の冷たい空気と、足元から立ち上がる暖気のコントラスト。頬に触れる風が澄み、街の音がクリアに聞こえる。
乾燥した冷気は鼻の奥まではっきりと入り、頭の内側までスッと通り抜ける。そして単純に空気がうまい。英語で言うところの “crisp air”だ。
急な寒さに触れた瞬間に湧く、あの説明のつかない高揚感。思わず身を縮めながらも、なぜか笑ってしまう、あの独特のテンションだ。ルーフを開けるとその感覚が一気に立ち上がり、オープンカーという“気分を上げる行為”をさらに後押ししてくれる。
「やっぱり冬こそオープンだよな」
そう思えるのも、暖房やシートヒーターがしっかり効く恩恵があってこそだ。
10年以上前のモデルとはいえ、フォルクスワーゲンらしい堅実さは健在で、暖房の立ち上がりも早く、走りも快適装備も不便に感じるところがほとんどない。
冬のオープンを楽しめる余裕がちゃんと備わっている。
今だからこそ
ザ・ビートル・カブリオレには独特の立ち位置がある。
フィアット500やルノー・トゥインゴのようなポップさを持ちつつ、ドイツ車らしい信頼性や使いやすさがきちんと根底にある。オープンモデルゆえの軽やかさもありつつ、日常で扱ったときの安心感は明らかにフォルクスワーゲンのものだ。
今回の個体は走行わずか2万5000km。
年式を考えれば極めて希少で、これからの時間を存分に共有できる余白が残っている。
平日の買い物にも、週末のちょっとした遠出にも無理なくつき合ってくれる。
そして、気が向いたときにルーフを開ければ、季節の匂いがそのまま車内に流れ込む。
それだけで、このクルマを選んぶ理由になる。
ビートルという名前に惹かれて乗る人も、形に惚れて手に取る人もいるだろう。いずれにせよ、特別なクルマを運転しているという感覚は、自然と湧き上がるはずだ。
ライフスタイルに溶け込む気軽さと、所有する喜びをちゃんと感じさせる存在感。ザ・ビートル・カブリオレはその両方を持っている。
忘れられつつある今こそ、あえて選びたい一台。
そして、このオープンカーを最も気持ちよく味わえる季節は、すぐそこまで来ている。

中園昌志 Masashi Nakazono
スペックや値段で優劣を決めるのではなく、ただ自分が面白いと思える車が好きで、日産エスカルゴから始まり、自分なりの愛車遍歴を重ねてきた。振り返ると、それぞれの車が、そのときの出来事や気持ちと結びついて記憶に残っている。新聞記者として文章と格闘し、ウェブ制作の現場でブランディングやマーケティングに向き合ってきた日々。そうした視点を活かしながら、ステータスや肩書きにとらわれず車を楽しむ仲間が増えていくきっかけを作りたい。そして、個性的な車たちとの出会いを、自分自身も楽しんでいきたい。