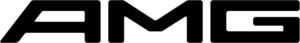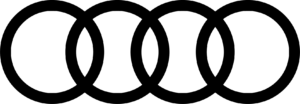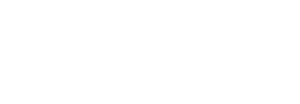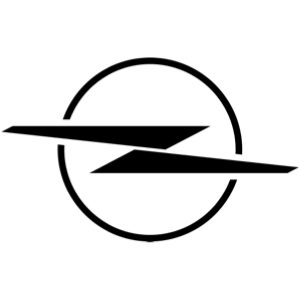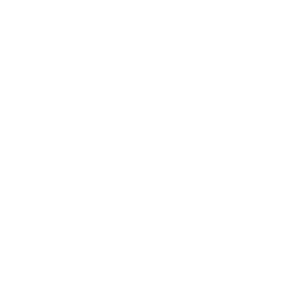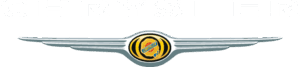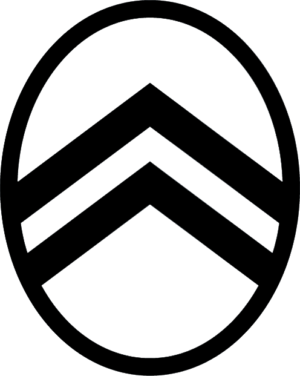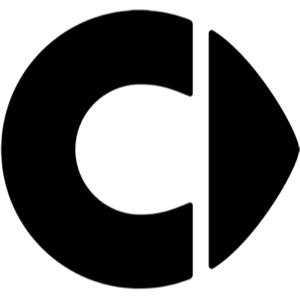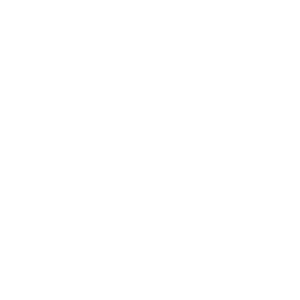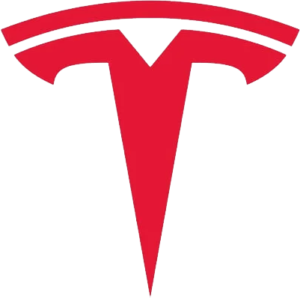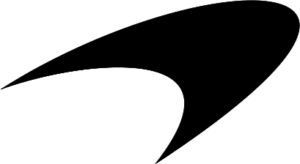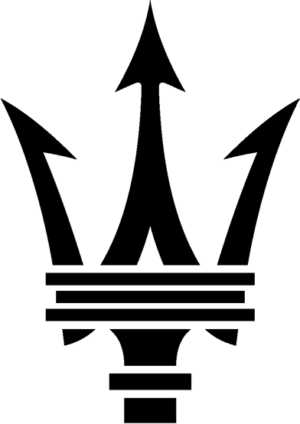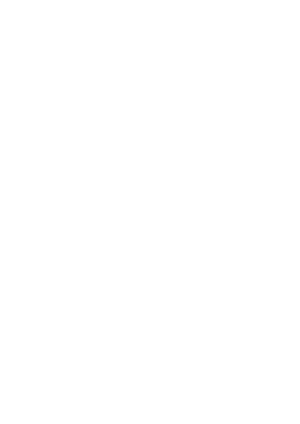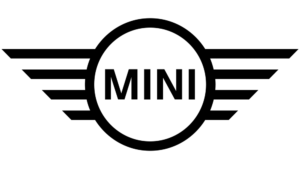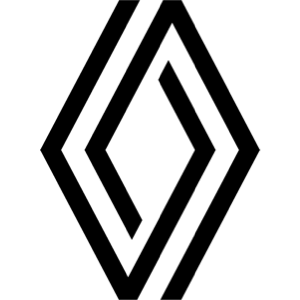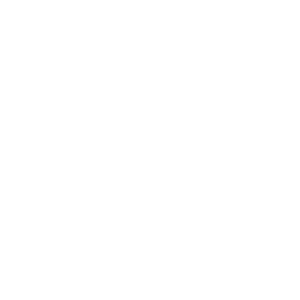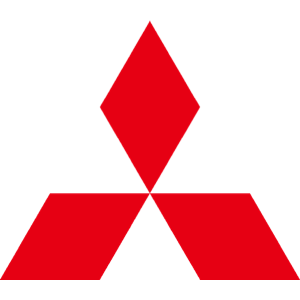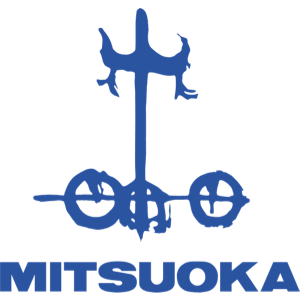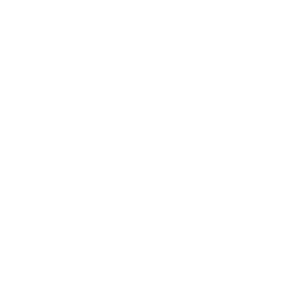自動車史を塗り替えた初代ロードスター。その文化的価値と走る喜びを、オリジナルを守り抜いた一台で、今あらためて味わう。
名車中の名車
自動車の歴史を振り返ると、「名車」と呼ばれる存在はいくつも思い浮かぶ。だが、その中でもユーノス・ロードスターほど“説明不要”なクルマはそう多くない。
1989年にデビューしたロードスターは、失われかけていたライトウェイトスポーツの市場を再び活気づけた存在だった。
コンパクトで軽量なボディにFRレイアウト、リトラクタブルヘッドライト。シンプルな構成ながら、人馬一体という言葉で象徴された「走る楽しさ」を真っ正面から提示した。
ヨーロッパではBMW・Z3、メルセデス・SLK、フィアット・バルケッタ、さらにはポルシェ・ボクスターまで、多くのフォロワーを生み出すことになった。
その影響は自動車業界にとどまらず、デザインやアートの分野でも賞賛された。
1998年にはニューヨーク近代美術館(MoMA)の永久コレクションに加えられ、プロダクトとしての純粋さと美しさを示す象徴的存在となった。
そんな、現代でも多くのファンに愛され続ける初代ロードスターが、ここにピュアな姿のまま残されている。
オリジナルコンディション
今回取り上げるのは、1993年式のユーノス・ロードスター。NA6CE型、つまり初代前期の最終年度にあたる一台だ。
1993年を境にロードスターは1.8リッターのNA8Cへ移行し、トルクを増した分だけ重量も増していった。だからこそ、このNA6CEは「1.6リッターならではの軽快さ」を最後に味わえる仕様でもある。前期の集大成と言っていい。
さらに、この個体が特別なのはそのコンディションにある。ワンオーナー、走行距離はわずか4.8万km。
しかも驚くべきことに、改造された形跡が見当たらない。シルバーストーンメタリックのボディは鈍い輝きを放ち、内装も純正然とした佇まいを残している。
30年を超えた今、これほど「そのままの姿」をとどめているロードスターは、もはや奇跡に近い。
いじって楽しむクルマだけど
ロードスターがカスタムされるのは、ある意味では自然なことだった。
デビュー当時から手頃な価格で、軽量ボディにシンプルな構造。社外パーツも豊富で、サーキットからストリートまでチューニングのベースとして理想的だった。
だから中古市場に出てくる個体の多くは、車高調やマフラー、エアロ、ホイール交換などでカスタムされている。エンジンチューンや後期パーツの流用も珍しくなく、それが付加価値として評価される面もあるだろう。
そんな中で、この個体は異端とも言える存在だ。
ワンオーナーであることを何より物語る、オリジナルのまま大切に維持されてきた姿。
ロードスターというモデルが「いじって楽しむクルマ」でもあった歴史を踏まえると、カスタムされていないこと自体が最大の稀少性を持つのかもしれない。
ピュアな本質を今こそ味わう
走行距離が5万kmに届かないということは、まだまだこれからも走れる余白を残しているということだ。30年経ったクラシックでありながら、日常的に乗れる現実性を持ち合わせている。
1.6リッターの自然吸気エンジンを回し、軽やかにシフトを繋ぐ。ハンドルを切れば、車体のすべてがドライバーの意思に追従する。余計な電子制御に頼らない、純粋なフィードバックが返ってくる。
それは単に懐古的な体験ではない。むしろ、現代のクルマに慣れた私たちにとって、忘れかけていた「走る喜び」を再発見する時間になる。
それと同時に、自動車業界のみならずアートやデザインの分野でも高く評価された、その文化的価値に触れるという体験。
1980年代後半、絶滅危惧種となっていたライトウェイトFRオープンカーの市場価値を、世界に再認識させたこと。そして、能面など日本的な美意識を取り込み、無駄を削ぎ落とした造形が世界的に評価されたこと。
まさにライトウェイトスポーツのマスターピースとして、ロードスターは自動車史に刻まれている。
そうした背景を持つロードスターのピュアな本質を、オリジナルのまま体感できる個体は、極めて稀だ。
このクルマは、ロードスターという存在の原点に再び出会わせてくれる。
SPEC
ユーノス・ロードスター 1.6
- 年式
- 1993年式
- 全長
- 3970mm
- 全幅
- 1675mm
- 全高
- 1235mm
- ホイールベース
- 2265mm
- 車重
- 940kg
- パワートレイン
- 1.6リッター直列4気筒
- トランスミッション
- 5速MT
- エンジン最高出力
- 120ps/6,500rpm
- エンジン最大トルク
- 137Nm/5,500rpm

中園昌志 Masashi Nakazono
スペックや値段で優劣を決めるのではなく、ただ自分が面白いと思える車が好きで、日産エスカルゴから始まり、自分なりの愛車遍歴を重ねてきた。振り返ると、それぞれの車が、そのときの出来事や気持ちと結びついて記憶に残っている。新聞記者として文章と格闘し、ウェブ制作の現場でブランディングやマーケティングに向き合ってきた日々。そうした視点を活かしながら、ステータスや肩書きにとらわれず車を楽しむ仲間が増えていくきっかけを作りたい。そして、個性的な車たちとの出会いを、自分自身も楽しんでいきたい。